 |
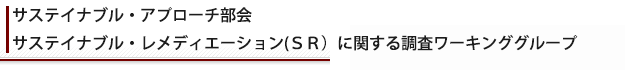
|
1.部会名:リスク評価モデルの普及・ツール化検討部会 活動期間:平成24年度〜平成25年度 活動の目的:わが国の土壌汚染対策におけるリスク評価の活用について普及・啓発をはかるため、 リスク評価を活用した土壌汚染対策に関する一般住民向けおよび技術者向けのガイダンス案をそれぞれ作成するとともに、 リスク評価モデルSERAMの改善・ツール化を行う。 2.部会名: リスク評価方法検証部会 活動期間:平成22年度〜平成23年度 活動の目的:リスク評価モデルSERAMの検証、リスク評価の活用のためのガイダンスおよびパラメーターの整備 3.部会名: リスク評価方法活用方法検討部会 活動期間:平成20年度〜平成21年度 活動の目的:わが国の土壌汚染対策におけるリスク評価の活用方法の検討、リスク評価モデルの検討 4.部会名: リスク評価適用性検討部会 活動期間:平成16年度〜平成19年度 活動の目的:欧米におけるリスク評価の実態調査、わが国でリスク評価を有効活用するための課題の抽出、欧米のリスク評価モデルの比較 5.部会名: 海外アセスメント・評価調査部会RBCA研究ワーキンググループ 活動期間:平成14年度〜平成15年度 活動の目的:米国で開発された土壌汚染対策のためのリスク評価モデル(ASTM E2081 : Risk-Based Corrective Action)の調査研究 |
